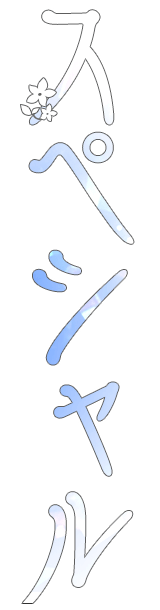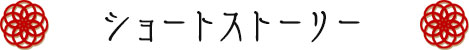「朱砂様! オランピア様との婚儀の日取りはお決まりでしょうか!?」
「……辰葱、玄葉あたりに唆されたな? 職場内での賭博は厳禁だぞ」
「えっ!? い、いえ……け、決して何月までに婚儀があるかを賭けてなど……」
彼は俺の秘書を務める辰葱。名誉のために言っておくが、普段は決して浮ついた言動など見えない真面目な男だ。
「いいか、辰葱。そんな冗談は絶対に余所で口にするなよ?」
「でも最近ずっと親しくされているではありませんか。コトワリの者達はお二人の婚儀が待ち遠しくて仕方がないんですよ」
俺は大きく溜め息をついた後、答えた。
「親しくしていることは認めよう。だがまだ彼女の口から『夫に』と告げられたわけではないのだ」
「そういうものなんですか……」
「そういうものだ。ほら、書類を渡せ」
「あ、はい! こちらです!」
手渡された報告書をめくり始めると、辰葱が少しだけ反省の見える顔で切り出した。
「あ、あの……決して朱砂様をからかったわけではないんですよ? お二人が本当にお似合いなので、早くちゃんとお祝いしたいだけなんです。皆もそうです」
「気持ちだけは受け取ろう」
「花婿捜しが始まった時から、いえ……朱砂様がオランピア様を助けたあの日から、絶対にお二人は結ばれるべきだと思っていたんですよ」
こんな彼は珍しい。普段は無駄口など殆ど叩かないのだ。それだけ彼女の一挙一動は注目の的なのだと改めて実感する。
「この島で、朱砂様以上に相応しい男性などいませんから」
彼が尊敬と誠意からそう言ってくれるのは分かっていた。だからこそ無下にはしたくなかったが、それで調子に乗れるほど俺は素直ではなかった。
「わざわざ花婿捜しなどせず、最初から朱砂様に決めてしまってもよかったのでは?」
「俺がそこまで自惚れ屋に見えるのか?」
「も、申し訳ありません……つい」
辰葱は信頼出来る男だ。実直で、愚かではない。だがそんな彼ですら、花婿捜しの本当の意味にはきっと気付いていない。この世界で、彼女だけが自由に恋することが出来る。
この世界で、彼女だけが自由に愛し、愛されることが出来る。
残酷な色の掟に縛られない───【白】の彼女だけが。
「彼女はずっと道摩屋敷に引きこもっていたのだ。少しくらいは世界を知ってもいいだろう」
「それは……確かにそうですね。手紙の配達を始められたのは驚きましたが」
『コトワリの所長さん! 本日も折り入ってお願いが!』興奮した面持ちで走り込んで来たあの日の彼女を、俺は忘れることなど出来ない。
『私、個人的な手紙配達をやろうと思うの』
何処かで予感していた、そう言い出すことを。
彼女は俺達と同じ志を持つ者だ。
未来を変えたいと願う者だ。
「しかも、黄泉の者達と仲良くやってるんですよね? それも驚きです」
地上と黄泉は隔てられている。クナドはいつも厳重に見張られていて、物資なども許可なく運び込めない。黄泉から地上へ手紙を出すことも、もちろん叶わない。そこに彼女が配達を始めると言い出したのだ。
「【白】のオランピア殿は慈悲深く、何にでも首を突っ込みたがりな上に、逞しくて破天荒なのだ」
「……朱砂様、顔がとても楽しげですよ。やはりオランピア様のことを……」
「【赤】の朱砂は彼女の愛を得たいと思っている、こう白状すれば満足か?」
辰葱の顔が真っ赤になった。「う、海が……光っているの?」
「素晴らしい、やはり俺も貴女も運がいい。これは本当に、滅多に見られないんですよ」
「何故? こんな海……初めてよ」
「これは、月光貝の光なのです」
「……月光貝? 貝が光っているということ?」
「そうです。正確には自ら光を放つのではなく、反射らしいのですが」
やはり彼女は俺と同じ側の人間だった。何かを変えるために、動かずにはいられない人間だった。
だから───愛した。
「ただ毎夜ではない。潮や月齢に関係がありそうですが、はっきりとした理由はまだ判明されていません」
「そんな貝があるなんて知らなかった。こんな美しい夜の海があるなんて……知らなかった」
青い光がちりばめられた美しい海を、彼女はじっと凝視めている。彼女だけが、自由に誰かを愛せる。
だからこそ───俺を愛して欲しかった。
俺の地位でなら、彼女の意見など一切聞かずに夫として名乗り出ることも可能だった。だがそんな形で彼女を得ても意味はない。
【白】の女は、愛したい者しか愛すことが出来ないのだから。
「……凄いわ、私はこの光景を絶対に忘れない」
「……不吉な言い方をしないで下さい。これから、幾らだって見られますよ」
その言葉を口にするのに、勇気が要った。まだ彼女に気取られてはならない。否、これからもずっと無関係でいて欲しい。皆を愛し愛され、島のあちこちを巡り、笑顔で手紙を届ける彼女であって欲しい。『今日こそ、その子を殺すがいい』
つまらぬ『神』とやらが、俺達に馬鹿馬鹿しい運命を押しつけた。
だが、そんなものくそくらえだ。
俺は愛したい女を愛すのだ。
俺は彼女を守り抜くのだ。
運命など、与えられた役目など、この手で葬り去ってやる。
俺は【赤】の朱砂───それ以外の何者でもない。