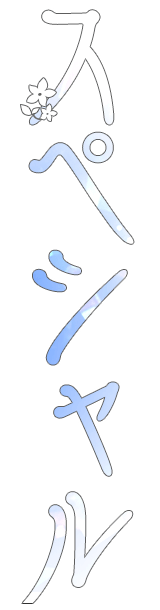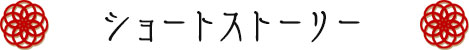「親愛なる兄上殿は、彼女に恋されましたね?」
唐突にそんな囁きが聞こえ、俺は飲んでいた酒を吹き出しそうになった。
「……なわけあるか」
「私の目を誤魔化せるとでも?」
目の前では、縁が婉然と微笑んでいた。兄上、なんて呼んではいるが、もちろん俺達に血の繋がりなんてない。ただこの黄泉で親のいないガキは珍しくなく、大人なんて一切あてにならない。だから気の合う者同士で兄弟、姉妹のように結びついて助け合う。縁は正確には黄泉の生まれではなく『とある事情』で上から落っこちてきた【紫】で、それでも妙に気が合ってずっとつるんでいる。
「オランピアの旦那は朱砂に決まってるだろ、それ以外に誰がいるんだ」
「でも彼女のこと、気に入ったろ?」
「……それを言うのなら、お前もだ。花占いしてやったり風呂に入れてやったり、珍しい菓子を食べさせたり、楽しげに相手してるじゃないか。地獄殿はどんな女からの誘いにも乗らない、ただ冷たく笑うだけ、なんだろ?」
「彼女は月黄泉の愛し子だ、丁重にもてなさなければ」
そう言って縁は豪華な絨毯に目を向けた。否───正しくはこの死菫城の地下に。この死菫城の地下には奈落と呼ばれる場所があり、あの月黄泉という男はそこでずっと暮らしているらしい。他人を悪く言いたくはないがどうにも得体の知れない男で、正直苦手だった。
「まぁ、殆どの者は朱砂に賭けてるね」
「お前はまたそんなことを」
「遊びだよ、単なる。たった一人の【白】が花婿捜しなんて始めたら、誰になるか皆が興味を持つのは当然だ」
「賭けになってない。朱砂に敵う男がいるとでも?」
「顔よし背丈よし、血筋よし、そしてコトワリの所長。朱砂は全く否の打ち所がない花婿候補だよねぇ」
「そうそう。早く交配して元気な子を産んでくれ、そうすれば俺もこの島の医師として安心出来る」
「兄さん、僕に隠しごとなんて無理だってば」
昔は可愛かったのに。小さく溜め息を洩らし、今度こそ酒を含む。
「……恋とか、そんなものじゃない。ただ稀少な【白】だ。医師として興味を持つのは当然だろ? あんなに見事に真っ白でさ、何処にいたって目を引く。本音を言えば、一度くらい寝てみたいと思ってるよ」
「あっそう」
彼は俺のグラスを奪い取り、半分くらい残っていたラムを一気に飲み干す。
「【黄緑】の薙草が彼女を狙ってるのは知ってるよね?」
「あの跳ねっ返りが、あんな奴を相手にするわけないだろ」
「目が泳いでるよ、兄さん」
縁はグラスになみなみとラムを注ぎ直し、俺の前に置いた。
「とにかく婿は朱砂に決まり! それが一番安心確実!」
「まぁ確かに朱砂もいつもと様子が違うよね。交配適齢期を迎えても、ずっと婚姻から逃げてたくせに」
「楽しみだ、二人の婚儀が」
笑みを浮かべてみせると、縁が大袈裟に顔をしかめてみせた。
「兄さんの応援をしようと思ったのに」
「要るか、そんなもの」
『信じなくてもいいけど、私はどんな男性にもこの躯を許したことはないわ』あの時、彼女は俺を睨みつけてそう言い切った。
【黄】の道摩の元で暮らしている【白】のオランピアは、閨の相手まで務めているに違いない───いかにも皆が好きそうな噂だ。 彼女が男を知らないのはすぐ分かった。いや、それどころか恋さえも。女だらけの奇妙な島で産まれ育ち、そこから連れ出された後は屋敷に引きこもっていた彼女は、身も心も真っ白だ。
俺は───こんなにも真っ黒なのに。
「僕は兄さんに賭けておくからね、頑張って」
血の繋がらない我が弟は、意味ありげに笑んで去って行った。そう───俺は真っ黒だ。
この島で【黒】は忌み嫌われる。陽の射さない闇の色、不吉な色。病気で髪や肌が黒くなろうものならば絶望して自ら命を絶つ者もいるくらいなのだ。当然ながら階級も低い。俺以外の【黒】は陽の射さぬ黄泉で暮らしている。
そんな俺が、太陽に最も近くて何もかも真っ白な彼女に愛されるはずなどない。
なのに。
『この島に必要な色だわ』
馬鹿なことを。
そんな真っ白なくせに、俺が図に乗るようなことを。
彼女に一番似合うのは朱砂だ。この島で一番信頼出来る男で、彼を婿に選べば絶対に幸せになれる。その上、あの月黄泉や道摩まで睨みを利かせている。真っ黒な俺など、彼女に近付いて欲しくないだろう。
なのに。
「そのイロハバナ、俺にくれないか。ちょっと成分を調べてみたいんだ」
「え? ああ! もちろんよ」
彼女が帽子の花に手をやったその瞬間───俺は触れてしまった。額にそっと口付けると、彼女の躯が固まった。真ん丸に目を見開いて、瞬きもせず立ち尽くしている。
「見事な額だから、つい」
「え……!?」
「良かった、泣かれたり殴られたり引っかかれたりしなくて」
「い、いま、あの……!」
これはちょっとした冗談だ。眩しくて無邪気な彼女をちょっとからかってみただけだ。道摩屋敷では山梔子が満開だ。その香りが甘過ぎるから、その花弁よりも真っ白な彼女の肌にちょっと触れたくなっただけだ。
そう、ちょっとした冗談で終わらせたかったのに。
オランピア、俺を愛してくれ。
だが真っ黒な俺など───愛さないでくれ。