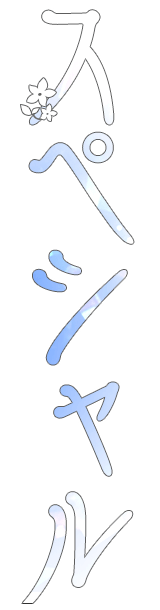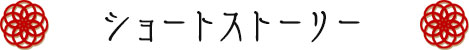「璃空、今から戻るのか」
長年の友人から声をかけられたのは、クナドでの勤務を終えて宿舎に戻る途中のことだった。
「朱砂! いいところに!」
「どうした璃空? 何かあったのか?」
「何かあったのか、じゃない! 何故、オランピアに手形など出した!? 一体どういうつもりだ!」
「欲しいだろうと思って」
あっさりと答えられ言葉を失っていると、朱砂は更に続けた。
「これからもクナドや黄泉で会うだろう。彼女をよろしく頼む」
「よろしく頼む、じゃない! 黄泉に出入りなどさせて何かあったらどうするつもりだ!」
「彼女が黄泉を気に入ったようだし、何かあれば縁もお前もいる」
俺はまた絶句し、朱砂を軽く睨んだ。地上と黄泉は巨大なクナドの鳥居によって隔てられている。昼夜交代で軍の見張りがいる他、通るには『手形』が必要だ。逆の言い方をすれば、そんなものを持たせてしまうと自由に出入り可能になる。
「……朱砂、彼女は稀少な【白】なのだろう? 黄泉で悪しき企てに巻き込まれでもしたらどうするつもりだ?」
「外に出なければ、肝心の婿を捜せないからな」
「そのことなのだが……わざわざ婿捜しなどさせなくとも、お前が相手になればいいだけだろう? この島で『【赤】の朱砂』ほど彼女に相応しい相手がいるか?」
彼は何も答えず、小さく笑んだだけだった。
「もしや朱砂……俺の言葉を侮辱と受け取ったか? そうではない、俺は心からお前を尊敬し、信頼している。だからこそ彼女に相応しいと思うのだ」
「分かっている、璃空。俺もお前のことを心から尊敬し、信頼している。この島にこの命ある限り、俺達は友だろう?」
血のような赤い髪、赤い瞳。濁りのないその色は彼の強さの証。この俺が───朱砂のようであったなら。
「俺は彼女にこの島を知って欲しいのだ」
赤い瞳には、期待が見え隠れしていた。彼が愚策を講じることはない。何らかの意図があるのだろうが、それでも毎日のように黄泉に行かせるのは賛成出来ない。
「璃空、お前はどうなのだ? 彼女のことをどう思う?」
問われたその瞬間。真珠色の髪が目の前で舞った気がした。
『今の聞いたでしょう? この人は黄泉のみんなや貴方のことを馬鹿にしたのよ!?』
女人に睨みつけられたのは初めてだった。彼女の全身から、俺への敵意が漲っていた。
彼女にとって俺は極悪人だ。この先もずっと恨むに違いない。だがそれは仕方のないことだ。俺は軍人で、この島の秩序を守るのが役目なのだから。
「馬鹿なことを尋ねるな、朱砂。俺の役目は……お前が一番よく知っているではないか。彼女の婿になることは有り得ない」
そう、俺の役目はもう定まっている。俺が一番よく分かっている。俺は───【青】の璃空。
「ここは……?」
「私の秘密の隠れ家なの」
「か、隠れ家? まさか……怪しい者など匿ってはいないだろうな」
「そんなことしてないわ、私一人しか使ってない。貴方が一番最初のお客様よ、さぁどうぞ」
「お、俺が……───最初?」
何故か、逃げ出したくなった。その『隠れ家』は、岬の一軒家だった。天女島に近い浜の上に建っていて、素晴らしく眺めがいい。
女人に睨まれたのも初めてなら、こんなふうに家に招かれたのも初めてだった。
眩しい陽射しの中、流木やら貝殻やら様々なものが飾られているのが見えて、それが彼女の大切なものだということはすぐに分かった。そんな彼女の大切なものを集めた場所に、俺などが立っていていいのだろうか。一番最初に入ってしまっても、いいのだろうか。
ひどく場違いに思えて、また逃げ出したくなる。
「い、今更だけど……あの舞を私などが教わっても大丈夫かしら。【青】の人だけに伝えるもの、というわけではないの?」
「舞の型だけなら問題はない。あれは卑流呼様に感謝を捧げ、死者を弔うものだから」
紆余曲折を経て、俺は彼女に舞を教えることになった。そのためにここに来たわけなのだ。
「ではまず、腕を前に出して」
「こう?」
「そのまま掌を……いや、対面だと分かりにくいかも知れないな。俺が後ろにつこう」
断じて誓うが、その瞬間まで一切下心などなかった。女人と二人きりになろうとか、肌に触れようとか、そんな不埒なことは一切考えていなかった。なのに。
「うわ!?」
後ろに回った途端、彼女の真珠色の髪が頬に触れた。それだけで俺は情けない声を上げてしまった。
「か、髪が……少し邪魔だな」
「ごめんなさい! 縛った方がいい?」
「いや、そのままで……───構わない」
何を言っているのだ、俺は。きっちり結ってもらえ、そうすれば俺に触れることはない。女人の髪に触れたのも初めてだった。長い髪なら自分のものを見飽きるほど見ているはずなのに、彼女の髪はずっと眺めていたかった。知らない花の香りがしていた。陽の光に透けて煌めくその髪は、厳かなくらい美しかった。
何を考えているのだ、俺は。
「指先が硬い、もう少し柔らかく」
「は、はい!」
「もう少し身体を後ろに引いて」
決して悪しき行いをしているわけではない。これは鍛錬だ。彼女が教えを乞い、それに応えただけのこと。ならばこの心臓の痛みはなんだろう。くすぐったいようにも、針で突かれたようにも感じる、この不可解なものは。
駄目だ、もう何も考えるな。
俺は尊き【青】の璃空。
故に彼女の花婿には───なれない。