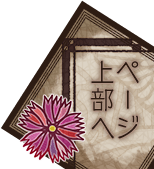- 久世ツグミ
- 「……んっ!?」
口の中に、再び薄荷糖の味が広がった。
つんと、甘く。
それはお互いの唇の味だ。
- 鵜飼昌吾
- 「嫁なら……僕が貰うから安心しろ」
- 久世ツグミ
- 「しょ……」
僅かだけ離れた唇から、そんな言葉が洩れた。
そしてまた口付けられる。
- 鵜飼昌吾
- 「……ん……っ」
最初は少し迷うようだったそれは、すぐに熱を孕む。
- 鵜飼昌吾
- 「それとも僕が夫では……不満だとでも?」
- 久世ツグミ
- 「ごめ……んなさい、そういう意味では……なくて……」
- 鵜飼昌吾
- 「なら問題ないな?」
その瞬間。
『今すぐ仕事を辞めてアパートを出て、
実家で花嫁修業して欲しい、と』
けれど今は、そんなことを考えたくなかった。
そんな問題があることを信じたくなかった。
- 久世ツグミ
- 「……昌吾、あの……ここで、こういう……ことは……神様の……罰が……あた……」
- 鵜飼昌吾
- 「少しだけ……ほんの少しだけだから……恐らく大丈夫だ」
それは一体どんな理屈かと思いつつも、
弁解する彼が妙に可愛らしくて抗えない。