――携帯が着信を告げる。
犬戒響の携帯電話は、ひどく実務的な連絡ツールとして使われている。
その理由は、私的な都合で彼に連絡を取れる人物が存在しないためだ。
国立緑尾学園高等学校に通う生徒には、それぞれ出席番号が割り振られたPCアドレスが与えられる。
クラスメイトから受ける最低限の学生らしい連絡や、授業内容に関する教師からの通達はそちらで充分に確認できる。
だから彼は、誰にも私用のアドレスを教えたことがない。
「――犬戒だ」
通話ボタンを押し、淡白な声で儀礼的に名乗る。
「ああ、高校にいる。指定時間外の連絡は避けてほしいんだが」
棘のある口調で言いながら、犬戒はまだ誰もいない教室を出た。
気の早い生徒はそろそろ登校してくる時間だ。
「定時報告は済ませたはずだ。まだ、何か?」
携帯のディスプレイに映る人物は彼の嫌味に動じない。
「……ああ。今のところ、変化の兆しは見られない」
通話相手の口上を『聞き流して構わない話か』と内心で判断しつつ、犬戒はそれと見えないような真面目腐った顔で適当な相槌を打つ。
静まり返った廊下に響くのは、その声と彼が立てる靴音だけだった。
「『鬼崎刀真』?」
通話を始めてから初めて、犬戒の表情に変化が生まれる。
「彼女のクラスに?」
即座に肯定が返され、犬戒は僅かに沈黙した。
相手の目的は容易に推測できる。変化が生まれないなら、自ら起こそうというのだ。
「新たな協力者、というわけか」
呟いた声音は抑えきれず皮肉なものとなる。
やがて専門棟に差しかかると犬戒は足を止めた。
目的地は『ここ』だ。
これ以上、歩き続ける理由はない。
「その鬼崎とやら、信用できるのか?」
彼の問いに通話相手は、肯定とも否定とも取れる返答をした。
婉曲的な言い回しは相手の癖だが、犬戒は予測した通りの意味を汲み取る。
つまり問題は、信じられるかどうかではなく、利用できるかどうかだけなのだ。
「――また連絡します、では」
携帯のディスプレイに慇懃無礼な笑顔を向けて、犬戒は強引に通話を終了する。
それは、背後から歩み寄る靴音を察知したためだった。
「あ……。すみません、電話中だったんですね」
犬戒が振り返ると、鴉取駿が申し訳なさそうな顔で立っていた。
用務員が見過ごしたのか、廊下の窓はひとつだけ開いている。
そこから吹き込む風が鴉取の髪をさらりとなびかせた。まるで絹糸のように美しい髪だ。月並みな比喩が似合うほど、鴉取は『綺麗』な姿かたちの人物だった。
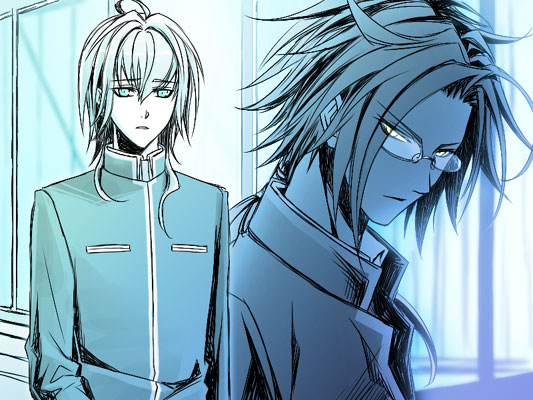
「単なる無駄話だ」
犬戒は携帯をしまうと面倒そうに答える。
彼を呼び出したのは犬戒だし、彼は時間通りに約束の場所へ来た。
いかに重要な話をしていたとしても鴉取に非はない。
「奴らは必要以上に手駒の動きを監視したがる」
「…………!」
連絡がどこからのものか匂わすと、鴉取は表情を硬いものにした。
だが、さしたる間を置かず、腹を決めたように相手を見据える。
「犬戒先輩。……僕に、何の用があるんですか?」
鴉取が立ち直るまでの時間は、犬戒の予測よりもずいぶんと早い。
見た目ほど弱くもないのかと失礼な感想を抱きつつ、犬戒は唇の端を持ち上げて軽く笑ってみせる。
「挨拶しようと思っただけだ。いずれ、仕事を共にすることもあるだろうしな」
含みのある口調で答えられ、鴉取は押し黙った。
本当にそれだけだろうか。
「おまえが寒名に招かれたのは【天意の巫女】の口添えだろう?」
釈然としない様子の鴉取を見て、犬戒は笑みを湛えたまま言葉を続けた。
「一体、何が気に入られたんだろうな」
「……僕は、ただ……」
彼女が気に入ったというなら自分より『弟』のほうだろう。
だが、鴉取は弟の存在を言い訳にしたくなかった。
「【力】があるだけです。……ただ、それだけです」
まるで、それが忌むべきことのように吐き捨てる。
「なるほど、よくわかった。おまえは馬鹿ではないらしい――」
犬戒から冷えた視線を受けて、鴉取は値踏みされているような気分になる。
実際のところ、彼は鴉取が受けた印象より、もっと露骨に『鴉取が利用できるか否か』を検討しているところだった。
だが、彼らの集中を削ぐように、強い風が音を立てて吹き込んでくる。
結論を出すのは少し早いか、と犬戒は思考を中断して視線を移す。
窓から見える校門の辺りを勤勉な学生たちが歩いていた。
もう校内に人が増え始める時間だ。
「……犬戒先輩」
彼の視線の先を追って鴉取が眉をひそめる。
犬戒が見ているのは藤森沙弥という名の少女らしい。
背の高い青年――鴉取は知らないが、大蛇凌だ――と共に校舎に向かっている。
「藤森さんがどうかしたんですか?」
鴉取が若干の警戒を込めて訊ねると、犬戒は鼻の先でせせら笑った。
「知り合いか? 見かけによらず手が早いな」
「そ、そういうのじゃありません! 藤森さんとは、温室で偶然会っただけで……」
彼女を変に巻き込みたくなくて、鴉取は咄嗟に否定した。
しかし、余計な情報を明かすのは不味いような気がして言葉を濁す。
「……彼女のことは、よく知りません。犬戒先輩こそ、藤森さんの知り合いなんですか?」
「ああ。何かと気になって、な」
慎重に問いかける鴉取に対して、犬戒は至極あっさりと頷いてみせた。
「気になる……?」
「はっきり言わせたいのか?」
犬戒は、藤森沙弥から視線を外す。
肩越しに鴉取を振り返りながら、やはり唇を歪めて簡潔に告げた。
「好きなんだ」
「――――」
鴉取は、妙に納得していた。
この男が信用できない理由がわかった気がする。
こうして話している間、ずっと、犬戒の目は笑っていない。
いかに口元が綻んでいようと、その瞳は感情を凍てつかせたままだ。
「どうした? 『信じられない』という顔だな」
「ええ。正直、意外でした」
鴉取は小さく苦笑しながら素直に頷いた。
追及しても、どうせ犬戒は答えないだろう。
……藤森沙弥は、優しい、ただの女の子だ。
まさか『彼ら』に目をつけられることはないだろう。
そう思いながらも、胸中から不吉な予感が消えることはない。
鴉取は、その姿が校舎に消えるまで、彼女のことを見つめ続けていた。
犬戒響の携帯電話は、ひどく実務的な連絡ツールとして使われている。
その理由は、私的な都合で彼に連絡を取れる人物が存在しないためだ。
国立緑尾学園高等学校に通う生徒には、それぞれ出席番号が割り振られたPCアドレスが与えられる。
クラスメイトから受ける最低限の学生らしい連絡や、授業内容に関する教師からの通達はそちらで充分に確認できる。
だから彼は、誰にも私用のアドレスを教えたことがない。
「――犬戒だ」
通話ボタンを押し、淡白な声で儀礼的に名乗る。
「ああ、高校にいる。指定時間外の連絡は避けてほしいんだが」
棘のある口調で言いながら、犬戒はまだ誰もいない教室を出た。
気の早い生徒はそろそろ登校してくる時間だ。
「定時報告は済ませたはずだ。まだ、何か?」
携帯のディスプレイに映る人物は彼の嫌味に動じない。
「……ああ。今のところ、変化の兆しは見られない」
通話相手の口上を『聞き流して構わない話か』と内心で判断しつつ、犬戒はそれと見えないような真面目腐った顔で適当な相槌を打つ。
静まり返った廊下に響くのは、その声と彼が立てる靴音だけだった。
「『鬼崎刀真』?」
通話を始めてから初めて、犬戒の表情に変化が生まれる。
「彼女のクラスに?」
即座に肯定が返され、犬戒は僅かに沈黙した。
相手の目的は容易に推測できる。変化が生まれないなら、自ら起こそうというのだ。
「新たな協力者、というわけか」
呟いた声音は抑えきれず皮肉なものとなる。
やがて専門棟に差しかかると犬戒は足を止めた。
目的地は『ここ』だ。
これ以上、歩き続ける理由はない。
「その鬼崎とやら、信用できるのか?」
彼の問いに通話相手は、肯定とも否定とも取れる返答をした。
婉曲的な言い回しは相手の癖だが、犬戒は予測した通りの意味を汲み取る。
つまり問題は、信じられるかどうかではなく、利用できるかどうかだけなのだ。
「――また連絡します、では」
携帯のディスプレイに慇懃無礼な笑顔を向けて、犬戒は強引に通話を終了する。
それは、背後から歩み寄る靴音を察知したためだった。
「あ……。すみません、電話中だったんですね」
犬戒が振り返ると、鴉取駿が申し訳なさそうな顔で立っていた。
用務員が見過ごしたのか、廊下の窓はひとつだけ開いている。
そこから吹き込む風が鴉取の髪をさらりとなびかせた。まるで絹糸のように美しい髪だ。月並みな比喩が似合うほど、鴉取は『綺麗』な姿かたちの人物だった。
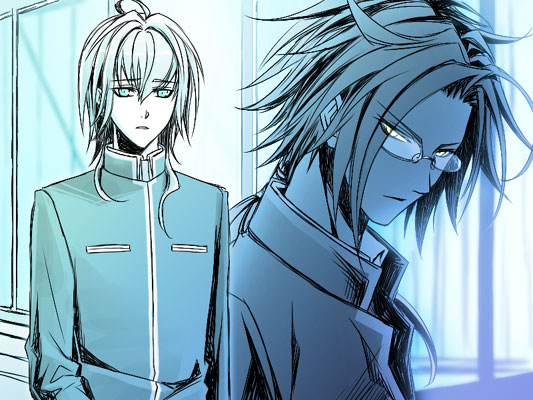
「単なる無駄話だ」
犬戒は携帯をしまうと面倒そうに答える。
彼を呼び出したのは犬戒だし、彼は時間通りに約束の場所へ来た。
いかに重要な話をしていたとしても鴉取に非はない。
「奴らは必要以上に手駒の動きを監視したがる」
「…………!」
連絡がどこからのものか匂わすと、鴉取は表情を硬いものにした。
だが、さしたる間を置かず、腹を決めたように相手を見据える。
「犬戒先輩。……僕に、何の用があるんですか?」
鴉取が立ち直るまでの時間は、犬戒の予測よりもずいぶんと早い。
見た目ほど弱くもないのかと失礼な感想を抱きつつ、犬戒は唇の端を持ち上げて軽く笑ってみせる。
「挨拶しようと思っただけだ。いずれ、仕事を共にすることもあるだろうしな」
含みのある口調で答えられ、鴉取は押し黙った。
本当にそれだけだろうか。
「おまえが寒名に招かれたのは【天意の巫女】の口添えだろう?」
釈然としない様子の鴉取を見て、犬戒は笑みを湛えたまま言葉を続けた。
「一体、何が気に入られたんだろうな」
「……僕は、ただ……」
彼女が気に入ったというなら自分より『弟』のほうだろう。
だが、鴉取は弟の存在を言い訳にしたくなかった。
「【力】があるだけです。……ただ、それだけです」
まるで、それが忌むべきことのように吐き捨てる。
「なるほど、よくわかった。おまえは馬鹿ではないらしい――」
犬戒から冷えた視線を受けて、鴉取は値踏みされているような気分になる。
実際のところ、彼は鴉取が受けた印象より、もっと露骨に『鴉取が利用できるか否か』を検討しているところだった。
だが、彼らの集中を削ぐように、強い風が音を立てて吹き込んでくる。
結論を出すのは少し早いか、と犬戒は思考を中断して視線を移す。
窓から見える校門の辺りを勤勉な学生たちが歩いていた。
もう校内に人が増え始める時間だ。
「……犬戒先輩」
彼の視線の先を追って鴉取が眉をひそめる。
犬戒が見ているのは藤森沙弥という名の少女らしい。
背の高い青年――鴉取は知らないが、大蛇凌だ――と共に校舎に向かっている。
「藤森さんがどうかしたんですか?」
鴉取が若干の警戒を込めて訊ねると、犬戒は鼻の先でせせら笑った。
「知り合いか? 見かけによらず手が早いな」
「そ、そういうのじゃありません! 藤森さんとは、温室で偶然会っただけで……」
彼女を変に巻き込みたくなくて、鴉取は咄嗟に否定した。
しかし、余計な情報を明かすのは不味いような気がして言葉を濁す。
「……彼女のことは、よく知りません。犬戒先輩こそ、藤森さんの知り合いなんですか?」
「ああ。何かと気になって、な」
慎重に問いかける鴉取に対して、犬戒は至極あっさりと頷いてみせた。
「気になる……?」
「はっきり言わせたいのか?」
犬戒は、藤森沙弥から視線を外す。
肩越しに鴉取を振り返りながら、やはり唇を歪めて簡潔に告げた。
「好きなんだ」
「――――」
鴉取は、妙に納得していた。
この男が信用できない理由がわかった気がする。
こうして話している間、ずっと、犬戒の目は笑っていない。
いかに口元が綻んでいようと、その瞳は感情を凍てつかせたままだ。
「どうした? 『信じられない』という顔だな」
「ええ。正直、意外でした」
鴉取は小さく苦笑しながら素直に頷いた。
追及しても、どうせ犬戒は答えないだろう。
……藤森沙弥は、優しい、ただの女の子だ。
まさか『彼ら』に目をつけられることはないだろう。
そう思いながらも、胸中から不吉な予感が消えることはない。
鴉取は、その姿が校舎に消えるまで、彼女のことを見つめ続けていた。