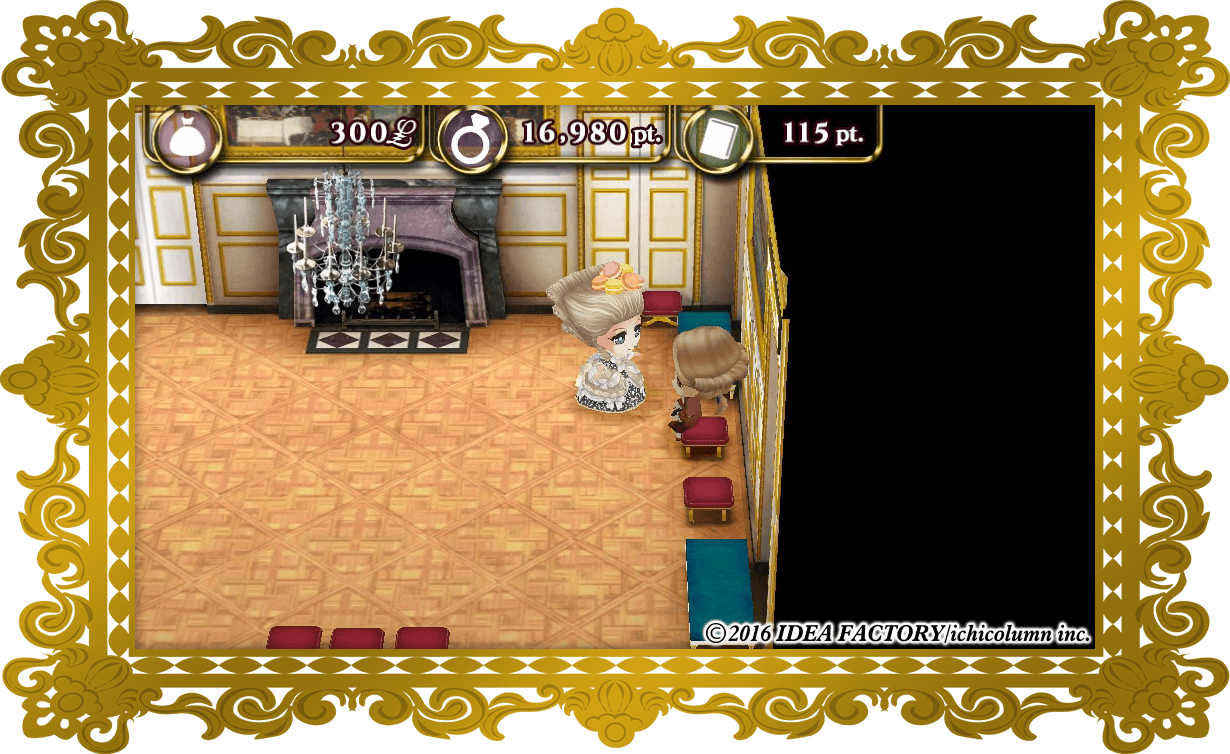
高木亜由美氏書き下ろし特別ショートストーリー
「un Moment dangereux」
「これはこれは王妃殿下。私に何のご用ですかな?」
「い、いえ特に用は……」
「その頭に載っているものは?」
「マカロン……ですわね。お一つ召し上がります?」
「王妃になって馬鹿に磨きがかかったか? おっと、これは失敬。つい言い過ぎたようだ」
何故こんな事になってしまったのだろうか。
「マリーお姉様! やっと見付けた! 捜したのだ! 今日はマカロンを作らせたのだ!」
数時間前にさかのぼる。エリザベート王女がマカロンを作らせたので皆で茶会をしようと誘ってきた。今日は天気がいい。絶好の茶会日和だ。ヴェルサイユ宮殿の庭園は貴族達がのんびりした時を楽しむのに格好の場所である。同行していたランバール夫人は賛成だと言い、エリザベート王女と共に茶会の話を進めるが、先程から王妃が沈んだ表情をしている。
「どうしたのだ? 何かあったのか……?」
「そんなに陛下がいらっしゃることが嫌ですの?」
「えっ!? い、いえ、その事ではなく……」
メルシー伯に何とかしてここで働けないかと相談していた件を思い出していた。今までアントワネットの身代わりとしてここに来るのはいいが、それではいつまで経っても王妃に仕える事が出来ない。マリア・テレジアとの約束を果たすなら、今のままではだめだ。ではどうするか……
「メルシー様に相談している事があって、それが心配なだけです。あっ、マカロンでしたよね!」
「そうなのだ! これから茶会を催そうと思うのだが、どうだろうか?」
「ええ、是非! では早速用意をして来ますね」
「分かった! 後で使いの者に呼びに行かせるのだ!」
王妃は茶会に参加する為に着替えをする事に。王妃が一日中同じドレスで居る事は少ない。午前と午後では衣装を変えるし来客や催し事があればその都度変える。それもここの慣例の一つである。
「アントワネット様、何か心配事でも?」
「……メルシー様にここで働けないか相談していたんです。私はここに来る前、皇太后様とずっとアントワネット様にお仕えすると約束していました。その約束を破りたくなくて……でも今のこの状態ではお仕えしているとは言えませんよね」
苦笑いをして見せる。仕えていると言えば仕えているのかもしれないが、きっと望む形ではないのだろう……ランバール夫人はその話題について、それ以上ふれなかった。
「はぁ……オレ、やっぱりこういうのは苦手なんだよなぁ」
「苦手とかそういう問題ではないかと思いますね」
「じゃあどんな問題なんだよ?」
普段より横暴なルイ16世。外出先から戻り王の部屋でくつろぐ。
「だってあなた、陛下に成りきるつもりがないでしょ?」
「あるって! 失礼だなぁ……これでも結構努力しているんだぜ?」
「そうは見えませんけどねぇ?」
「努力してるんだっつーの! ったく……」
襟元をゆるめ、ソファにドカッと腰を下ろす。国王陛下になったばかりのダントンは、王妃にプチ・トリアノンを“渡して”きた所だ。最初は菓子か何かの名前だと思っていたが、それが建物の名前だと知り驚いた。そんな具合だから身近にいたフェルゼンを無理矢理同行させ、先程戻って来たという訳だ。
「陛下、ラファイエット侯がお見えです」
「通してよいぞ」
「畏まりました」
ダントン陛下はどうだ?と偉そうにして見せるがフェルゼンは呆れてため息を吐く。自分なりに成りきって返答したつもりだった彼は、何処がどう違うのか言ってみろと迫る。
「何処がどうって、たかが返事をした程度でいちいち偉そうな態度を取られてもねぇ……」
そこにラファイエットが入ってくる。
「……何故フェルゼンがここに居る?」
「先程プチ・トリアノンに行って来たところでしてね。私は陛下に無理矢理連れて行かれただけですよ」
「だってよぉ、プチ・トリアノンが何なのかフツーは知らねぇって。それで、何かあったのか?」
聞くと、本物の国王陛下はこれからパリへ赴き、本物の王妃が滞在しているフォルタン・ホテルへ様子を見に出掛けるという。
「その後はロゼール伯の用意した屋敷に移動となるが、私はここに残る為様子を見に来ただけだ」
「何でお前が同行しないんだ?」
「ラファイエットが同行したら、“陛下”には誰が同行するんです?」
「あ、そっか」
普段国王の側には常にラファイエットが付いている。今日の予定は晩餐会だけだが明日はパリで公式訪問がある。その準備もあり今はここを離れるわけにはいかない。それに国王、ルイ16世の護衛はロゼール伯爵に任せてあるので一応安心していた。本当は彼を信じ任せる他なかったと言った方が適切かもしれない。事情を知らない衛兵では護衛は任せられない。何しろ国王は庶民に扮するのだから。
「この後の予定は分かっているんだろうな?」
そう言われ、頼りない国王陛下はポケットからメモを取り出し確認する。そこには廷臣達との晩餐会、翌日公式訪問、と書かれてあった。
「はぁ~、晩餐会か……」
「せいぜいばれないように頑張って下さい。では私はこれで」
自分の用は済んだとばかりにフェルゼンは退散する。
「これじゃ自分のしたい事をする以前の問題だよなぁ……慣れるだけで数日かかりそうだ」
「数日? 数年の間違いだろう」
ダントンは素直にその言葉を認めた。
頭を抱えながら昼過ぎやっと起床したオルレアン公。ヴェルサイユ宮殿に来るはずではなかったが御者に知らずに命じていたのだろう。重い身体を起こしカーテンを開けると陽の光に顔をしかめた。
「お目覚めで御座いますか?」
「……おい、薬を持ってこい。酒の呑み過ぎで頭が痛い」
「畏まりました。あの……」
行動しない侍女を睨む。
「い、いえ! 何でもありません! すぐにお持ち致します!」
深いため息を吐く。こんな呪わしく腹立たしい場所から一刻も早く去らねばならない。薬を飲み身支度を簡単に済ませ、パリに戻ろうとしたオルレアン公の足を再びヴェルサイユ宮殿に向けさせたのは、愛人への約束であった。
「はぁ……そうだった、その為にここに来たんだったな……すっかり忘れていた」
朝まで愛人と酒を呑んで過ごしていた彼は、つい勢いで王妃専属の髪結師に髪を結わせると言ってしまったのだ。時々自分で自分が嫌になるのはこういう時だ。
「たかがあいつの為に何故この私が動かねばならないのか……」
まだ薬も効かず酒の抜け切らない身体を動かし、レオナールを呼んで来る様命じた。
着替えを終えた王妃はランバール夫人を伴い、茶会会場へと足を運ぶ。
「それにしてもよかったですね」
「侍女長の件ですか? ええ、とっても嬉しいですわ」
「召使いはもう付けたのですか?」
「目当ての子は居ますのよ。あとは……」
「あっ……先に行っていて下さい! すぐに行きます!」
何か用を思い出したのか、誰かを見付けたのか……王妃は足早に去る。従者や他の侍女が追い掛けようとするがランバール夫人が止めた。宮殿の中なら問題はないだろうしこれから向かうのはお茶を飲み、マカロンを食べながら話をする場所。エリザベート王女とゆっくり待つことにした。
庶民風の格好をしたルイ16世らしき人物の所まで行き、「陛下」と声を掛けるが睨まれる。
「見て分からないのか? 今はジャックだ」
「あ、そ、そうでしたね……」
お忍びで出掛ける国王に、その正体を明かす呼び方は失言であった……が、何処をどうみてもやはりルイ16世だ。一応深々と帽子をかぶってはいるが。
「予定ではもっと早く出る予定だったが、この衣装が見付からなかったので手間取った」
「なるほど……それでどちらへ?」
ルイ16世こと庶民のジャックから離れた場所にラファイエットが立っていて咳払いをされる。王妃が庶民に声を掛ける事はあり得ない、そういう咳払いであった。それを察した王妃は無言でその場を後にする。
「……何故ばれたのだ?」
「まぁ、致し方ないでしょうな」
相手は庶民なので後ろで腕を組み偉そうな態度をしているラファイエットも、態度と言葉が釣り合っておらずぎこちない。
「以前とは違い今回は帽子をかぶっているのだが。仮面でも付けた方がよいか?」
「お止めになった方がよいかと。陛下、そろそ……」
「ごほん」
「ジャック殿、そろそろ参りましょう。馬車までお送り致します」
「うむ」
ジャックはパリに向け出立した。
「ねぇ、さっきの陛下でしょ?」
振り向くと召使いのエルザが立っていた。茶会会場になかなか到着しない王妃をエルザが呼びに来ていた。
「あ、うん。たぶん宿に行ったんじゃないかな」
「ふーん……あんたも気を付けなよ? 陛下以上に怪しいから」
「えっ!? そ、そうだよね……」
見た目はそっくりでも言葉遣いや声も違う、性格も違えばいくら病と言われても普通の者なら怪しむ。まるで別人のようだと。
エルザに案内されて庭園へ向かう。二人だけなので道中気さくに会話していると、目の前から背の高いご婦人……ではなく紳士が小走りで迫ってきた。
「まぁ~、アントワネット様! ご機嫌うるわしゅう御座いますわ!」
王妃専属の髪結師レオナールだ。
「オルレアン公に呼ばれちゃったの。アタシ、この後も予約が入っていますのよ? それなのに急用だから……ですって。あの方に呼ばれたらさすがに断る訳にはいきませんもの」
王妃専属とはなっているが、正確には王妃を優先ぐらいの意味で普段用がない時は他の婦人達の髪を結っている。
「オルレアン公爵様がレオナールを呼び出す? ってことは……愛人の髪でも結わせる気かなぁ?」
「ちょっとアンタ! 召使いのクセに馴れ馴れしいわよ!」
「あ、あの! 私、急いでいますので失礼しますわ! 行きましょ」
今でも怪しまれているがこれ以上喋っては余計怪しまれる、そう思った王妃はレオナールを置いて庭園へ急いだ。
「……やっぱり変なのよねぇ。ま、いいわ。アタシも急がなきゃ!」
レオナールが呼ばれた部屋に入ると、気だるそうなオルレアン公が座っていた。急いで来た相手の顔を見ることなく「明日パリの屋敷に来い」とだけ言われる。
「あの~……明日はパリの公式訪問があるので……」
「あいつらと私とどちらが大事かよく考えろ。命は一つしかないからな」
「うっ……そ、それじゃあ午後ならいかがかしら? 午後ならパリにいますし、手の空いた時なら……」
「何度も言わせるな。どちらが大事かよく考えろと言ったはずだぞ?」
一瞬たじろぐが王妃に仕えてこそ最高の髪結師なのだと自負している彼は、オルレアン公と王妃を比べる訳にはいかない。貴族達の髪を結っても自分の美を理解する客とは出会えなかったが、ここにきてやっと彼の美の理解者と出会えた。その王妃を裏切る事は彼の美を否定する事になる。
「……アタシはアントワネット様の髪結師ですわ。では失礼~!」
「お、おい!」
止める声も聞かず部屋を出た。もちろんオルレアン公の腹の虫が治まるはずがない。
「もうね! 足はガクガクするし鼓動はダントン様が近くに居た時みたいに早くなるし!」
茶会に乱入したレオナールは、目の前のマカロンを口に詰め込み動揺を抑えようとしていた。
「だってアタシはアントワネット様の髪結師なのよ!? しかも明日は大事な公式訪問の日! 受けられる訳な……ふぐっ! お、おぢゃ……死んぢゃう~!」
「は、早く飲むのだ!」
一同はとりあえず彼が落ち着くまで待つことにした。その後詳しい事情を聞くが、ランバール夫人はどう考えても王妃に対する嫌がらせだと言い、レオナールもそれに賛同する。
「では、わざわざ嫌がらせをする為にここに来たのですか?」
「さぁねぇ……何だかだるそうにしていたわね。それに……そうそう、部屋中酒の匂いで臭いったらなかったわ」
オルレアン公の事情はよく分からないが、王妃より自分の方が格上だと誇示した事には変わりない。本物のアントワネットなら直接彼の所に乗り込むかもしれないが。
「ここはアントワネット様の力で追い返すべきよ!」
「ええっ!? わ、私!?」
「無理ですわ! アントワネット様が騒ぎを起こせばアントワネット様が迷惑しますのよ!?」
「な、何それ……本人が騒ぎを起こすのに本人が迷惑ですって?」
ランバール夫人はまずい事を言ってしまったという顔をしてうつむく。
「私もオルレアン公は苦手なのだ……しかし、ここまで露骨に嫌がらせをするとは……」
今度はゆっくりとマカロンを口に運ぶレオナールは、はっと何かを思い付いたようで、マカロンを自分の頭に載せてみせる。エリザベート王女達はその姿を見て一斉にお茶を吹き出した。
「な、何をして……」
「……そうよ、これよ! これだわ!」
結局腹の虫の治まり所がなかったオルレアン公は、王妃に嫌味を言ってからパリに戻る事にした。数いる愛人一人の為に自分が躍起になっている事自体が滑稽だ。髪結師の件などどうでもよい、今は自分の怒りを鎮めることしか考えないようにした。しかし……
「くそっ……まだ効かないのか! おい! 頭痛に効く薬を出来るだけ持ってこい!」
「は、はっ……!」
そう言うと控えの間の椅子に座る。深酒は金輪際しないと決めた瞬間であった。
「陛下、廷臣達との晩餐会についてですが」
「分かっておる。晩餐って晩メシの事ではないか。笑顔で食べていれば問題あるまい! ははは!」
何も分かっていない国王だがラファイエットが説明する訳にもいかない。だがある意味当たっていた。笑顔で“黙って”余計な事をせず、ただ食べていれば問題はない。それよりもパリに行ったルイが気掛かりだった。
「おい、あれは……あれ見ろよ。ほら」
控えの間を通ろうとした時、二人の目に王妃とオルレアン公の姿が飛び込んできた。非常に珍しい組み合わせだ。
「これはこれは王妃殿下。私に何のご用ですかな?」
「い、いえ特に用は……」
「その頭に載っているものは?」
「マカロン……ですわね。お一つ召し上がります?」
「王妃になって馬鹿に磨きがかかったか? おっと、これは失敬。つい言い過ぎたようだ」
「ご存じありませんか? 今ヴェルサイユで流行している髪飾りですのよ」
「そんな事には興味がない」
レオナールの計画でこうしているのだが既に雲行きが怪しくなっていた。頭の上にマカロンを載せてこれが最新のモードだと説明する事で会話の切っ掛けを作り、あわよくば彼の愛人に真似をさせる。本当の目的は頭の上に載っているマカロンを食べさせるという、無謀で無茶であまり意味がないような、だが難度だけは高い計画であった。ちなみにマカロンには全て下剤が仕込まれている。
「王妃、一つ忠告しておきましょう。あの髪結師は即刻殺した方がよい」
「な、何故でしょうか……?」
「よいからさっさと処分しろ。庶民をここに入れるからこんな事になったのだ! ……まぁよい。王妃や陛下が痛い目に遭うのはこの私の望む所でしてな」
最初は萎縮して接していた相手だが、人をモノのように扱うぞんざいな言い方に段々腹が立ってきた。そこに二人の様子を伺っていた国王とラファイエット侯爵が仲裁に入る。
「何か御座いましたかな? オルレアン公」
「陛下も物好きですな。菓子を頭に載せ、しかもそれを食べろと言われていた所でしてな。全く、これだからオーストリアの野蛮な女は」
「ぷっ、頭に菓子を載せて食べろって? 変わってるなぁ、アンタ……っと、そ、そういう所が王妃のよい所だ。うむ」
声や言い方がダントンに似ている気がするが……
「陛下、お時間です」
「すまんな、これから廷臣達と食事をせねばならないのである。えー……妻のした事は大目に見てやってくれ。これも愛情表現の一つだからさ。って事で~、余が一つ食してやろう」
……この後晩餐会が中断されたのは言うまでもない。
一方その頃。パリ、フォルタン・ホテル。
「ただいま。……何だ、来ていたのか。荷物を引き取りに来たのか?」
宿の部屋に引き籠もっている本物の王妃を荷物と呼ぶロベスピエール。
「様子を見に来ただけだ。余はこれからロゼール伯の所へ向かう」
「おれの護衛付きだぜ? 完璧だろ?」
ジョエルの言う事には全く相手にせず、しかも国王陛下(一応変装しているが)が来ているのにそっけない返事をしただけで部屋へ戻ろうとする。
「ジョエルー、ちょっと手伝ってくれる? いつもお世話になっているロゼール様に差し上げたいものがあるのよ。あら、お帰りなさい。食事は?」
「後で貰う」
日常の何でもないクロエとロベスピエールの会話。ジャックにとってはそれが心地良かった。
「王サマ、ちょっと待ってろよ。すぐに戻る」
「分かった」
ジョエルが部屋に入っていくのを見届けると、ロベスピエールは宮殿の様子をジャックに尋ねる。詳しい様子を見る事なく出て来たので分からないと答えると、ロベスピエールは腕を組んで言った。
「あいつじゃ周りに振り回されて終わるだろうな。メシは? まだだろ?」
「そうだ」
「だったら食べて行けよ」
「そなたが作るのか?」
「何の冗談だ?」
「聞いてみただけだ」
ジャックはもうしばらく宿に滞在する事にした。
※無断転用・無断転載はご遠慮ください。