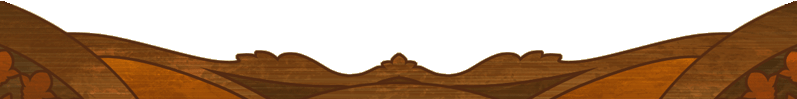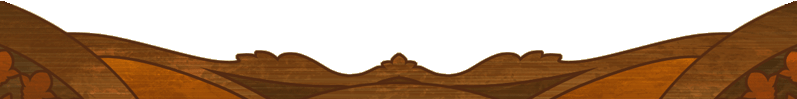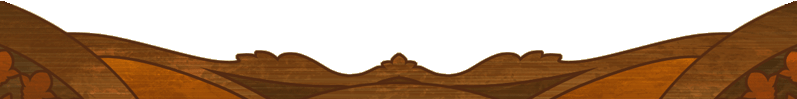「ただいま〜! ごめんね、遅くなっちゃって」
顔が隠れる程大きな荷物を抱えたティアナに、白いお尻を振りながらルシアが歩み寄る。
「まったく、どこをほっつき歩いてたんだよ。お前がいない間、色々大変だったんだからな!」
「え? 大変って?」
器用に床を蹴りながらその後を追って来たエリクは、申し訳なさそうな顔でティアナを見上げた。
「大したことじゃないよ。ちょっとクラウスが来てただけで」
「どこが大したことないんだよ。金の粉の効果が切れるのがもう少し早かったら、やばかったじゃねーか!」
「そうだとしても、別にティアナのせいじゃないし! どうしてルシアって、いつもそういう言い方しかできないの?」
「そうだな。ティアナがいなくて寂しかったなら、素直にそう口にすべきだ」
ゆっくりと目を閉じ頷くアルフレートに、ルシアは両目を吊り上げた。
「寂しくなんかねーよ!! ただちょっと帰りが遅いから、心配して……」
「ふふ、なーんだ。じゃあ心配してたって、ちゃんと言えばいいのに」
「その通りだな。もっと素直になれ、ルシア」
「っ……テメェら、人の気も知らねーで、好き勝手言いやがって……っ!!」
「え、ええと……」
そんな3匹を見下ろしながら困惑気味のティアナに、マティアスはゆっくりと首を左右に振る。
「安心しろ、この姿になるところを見られたわけじゃない。それより早く荷物を下ろしたらどうだ」
指摘され、ようやくティアナは抱えていた荷物を長椅子に下ろした。
「それで、クラウスの用事って、なんだったの?」
均衡を崩し床に倒れそうになる荷物を慌てて前足で押さえながら、マティアスは小さく鼻を鳴らす。
「カトライア国民から寄せられた質問状とやらを持って来ただけだ。どれもこれも低俗な内容の物ばかりだったが……そろそろ回答を取りに来るかもしれない」
「質問状……?」
マティアスの説明では今ひとつ状況を理解できなかったが、机の上に広げられた紙の束を手に取ったティアナの顔に、次第に苦笑いが浮かぶ。
「それで、金の粉はどこにあるんだよ。ちゃんと買って来たんだろ?」
「あ、ちょっと待って、ルシア……!」
大きな袋にくちばしを突っ込み強引に中身を物色し始めるルシアの身体を、ティアナは慌てて抱き上げた。
「金の粉はその袋の中じゃなくて……」
「よっしゃ、いただき〜!」
ルシアは、差し出された小さな袋を素早く奪い口に咥える。
だが、そのまま金の粉を持ち去ろうとしたアヒルの背を、アルフレートの前足が押さえつけた。
「ぐえっ……! 何すんだよっ!」
「金の粉は4人で公平に分配する決まりだ」
「その“公平に”が信用できねーんだよ! いつもオレの分だけ妙に少ないのは、絶対気のせいじゃねぇ!」
「アヒルとライオンでは、身体の大きさが違うからな」
ルシアから金の粉を奪い、マティアスはアルフレートに目配せする。
ようやく解放されたルシアは、大きく羽をばたつかせながら口を尖らせた。
「あのなぁ、デカイからってたくさん必要なわけじゃねーってのは、オレの身体で散々実験済みだろーがっ!!」
「ぐだぐだうるさいアヒルだな。そんなに肉屋に売られたいのか」
「ふっ……何度も同じ脅し文句でビビると思うなよ。そういうマティアスこそ、闘技場送りにしてやってもいいんだぜ?」
「ちょっと、いい加減に止めてよ2人とも! 今日はすることがたくさんあるんだから!」
エリクは、何か言いたげな顔で長椅子の上でぐらついている買い物袋に視線を移す。
その意味に気付いて、アルフレートが口を開いた。
「ところでティアナ。頼んだ物は全て見つかったのか?」
「うん。多分全部買えたと思うけど……」
「ご苦労だった。代金は後でファザーンに請求しておいてくれ」
そう言いながら、マティアスは少し屈めた頭の後ろで、ティアナの身体を部屋の外へ押し出そうとする。
「ちょ、ちょっとマティアス? どうしたの?」
「どうもしない。しばらく2階でのんびりしていろ」
「え? のんびりって……そろそろ夕食の支度をしないと」
「お前は何もしなくていい。後は俺たちに任せておけ」
「そうそう、たまにはティアナをゆっくりさせてあげようと思って!」
側まで近づくと、エリクもマティアスに倣い小さな前足でティアナの身体を押す。
「感謝しろよティアナ。ファザーンの王子4人にメシを作らせる女なんて、この大陸中探してもお前しかいねーんだからな」
「もうルシア! そういう言い方はダメだって注意したばかりなのに!」
拗ねたようにそっぽを向くルシアにエリクは頬を膨らませるが、ティアナは状況を理解できず、それぞれの顔を見渡す。
「4人でご飯って……まさか、マティアスたちが料理をする気なの!?」
「ああ。何か問題があるのか?」
その顔にありありと不安の色が浮かんだのを見て、マティアスは不機嫌そうに目を細める。
「安心しろ、ティアナ。オレの手料理は城の兵士たちに評判がいいんだ」
ティアナはしばらく戸惑っていたが、アルフレートが自信ありげに胸を張ったのを見て、ようやく微笑む。
「みんな……ありがとう。でも、本当にいいの?」
「大丈夫だって言ってるだろ。ほら、さっさと行けって」
短い足を持ち上げ、ルシアはティアナの身体を部屋から押し出そうとする。
そんな仕草に苦笑しながら、ティアナは4匹に背を向けた。
「ふふ、わかった。じゃあ今日は、ゆっくりさせてもらうね」
居間の戸が閉まり、ティアナが階段を上る足音が遠のいたのを確認したマティアスは、金の粉が入った袋を器用に前足で掬い上げ、それを身体に振りかけた。
ゆるく結ばれた口から金色の粉が舞い、次第にライオンの輪郭がぼやける。
部屋を満たしていた目映い光が収束する頃、その猛獣に代わりすらりとした体躯の青年が現れ、長い金色の髪を無造作にかき上げた。
「一時的なものとはいえ、やはり人の姿になるとほっとするな」
小さくため息をつきながら、マティアスは早く自分たちにもと押し寄せるルシアたちの身体に、同じ粉を振りかける。
ようやく呪いから解放された3人は、それぞれの顔の安堵の表情を浮かべた。
「時間がない、さっそく始めるぞ」
長椅子に寝そべっていた紙袋を軽々と持ち上げるアルフレートの後に、エリクが続く。
「ふふ、頑張ろうねアルフレート! 僕は野菜を切るね!」
「任せたぞ。俺はここでお前たちがつまみ食いをしないかどうか、しっかり監視しておいてやる」
台所に入るなりどっかりと椅子に腰を下ろすマティアスに、ルシアは頬を引きつらせた。
「いい加減にしろよ、マティアス……。人のことばっかりこき使ってねーで、たまには身体を動かせ!」
「わかったわかった。味見くらいはしてやるから、料理ができ次第俺の前に持ってこい」
「おいエリク、ちょっとその包丁貸してくれ」
「だ、ダメだよルシア! ここはちゃんと4人で協力しないと!」
「エリクの言う通りだ、マティアス。他ならぬティアナのためだろう」
包丁を手にしたルシアと涙目のエリクに詰め寄られ、ようやくマティアスは重い腰を上げる。
「まったく……次期ファザーンの王であるこの俺を、台所に立たせるとは……」
ぶつぶつと呟きながら袋の中を漁っていたマティアスは、白い紙に包まれた何かを取り出し、ニヤリと口の端をつり上げた。
「中々いい肉じゃないか。焼いて食うだけでも十分美味そうだが、今日は煮込みにするか」
マティアスは手にした肉の固まりを、ぐつぐつと野菜が煮える鍋の中に放り込む。
「あ、あああ〜〜〜〜!!」
「っ……!? な、なんだよ、突然でけー声出すな!」
エリクの鋭い悲鳴に驚き、ルシアはジャガイモの皮を剥く手を止め振り向いた。
「ちょっと止めてよマティアス! このお鍋は野菜スープを作ってるところなんだから!」
「野菜スープだと? そんな物で腹が膨れるか。男なら肉を食え」
「この料理は、ティアナのために作ってるんだよ? それに、こんなに大きなお肉が丸ごと入ってる料理なんて、ティアナが喜ぶはずないよ!」
「なぜそう決めつける。ティアナもああ見えて意外と肉食かもしれないぞ」
「そんなことないよ! 絶対野菜の方が好きだと思う!」
「いいや、肉だ」
「野菜ったら野菜!!」
「あー、うぜぇ。肉でも野菜でもどっちでもいいから、口を動かす前に手を動かしてくれよ……」
ゲンナリとため息をつくルシアの隣で、静かにアルフレートが頷く。
だがそれでも、2人の言い争いは収まらなかった。
「とにかく、この料理は肉の煮込みに変更だ。野菜は捨てろ」
「ダメだよ! 元々僕が作ってたんだから、捨てるならお肉!」
エリクとマティアスは、お互いに鍋を手にしたまま睨み合う。
黙ってそれを聞いていたアルフレートは、小さく息を吐き、その間に割って入った。
「お前たち、いい加減に好き嫌いは止めろ。健康のためには、肉も野菜も両方きちんと食うべきだ」
「うるさいぞ、雑食」
「ざ、雑食……!?」
「お前も、どちらかというと肉の方が好きだろう?」
「そんなことないよね? 野菜の方が好きだよね?」
仲裁に入ったはずのアルフレートは、2人に挟まれたままおろおろと視線を彷徨わせる。
「まったく、お前らなんにもわかっちゃいねーんだな」
何かを悟ったかのような余裕の笑みを浮かべ、ルシアは手にした物を鍋の中に放り込む。
「え!? ちょ、ちょっとルシア……!?」
「お前、何を……!」
「ティアナの本当の好物は、魚だ。間違いねぇ」
3人が恐る恐る鍋の中を覗き込むと、大きな肉の固まりに絡み合うように、細長く黒い物体がうごめく。
「おい、ルシア……。これはなんだ」
「見りゃわかるだろ、ウナギだよ」
「ええ!? ウナギ!?」
もう一度恐る恐る鍋の中を確認した後、エリクとマティアスはげんなりとした顔で目を伏せる。
「な、なんだよその顔は! 肉も野菜も魚もいっぺんに取れて、すげーいい料理じゃねーか!」
「しかし、見た目は最悪だな」
静かに首を振るアルフレートに、ルシアは頬を引きつらせながら反論する。
「見た目なんて関係ねーよ! 重要なのは味だろ! お前だって見た目より内面を磨けとかいつも言ってるじゃねーか!」
「それとこれとは話が違う」
「ああ、ティアナの浮かない顔が目に浮かぶようだ」
神妙な顔で頷くマティアスの隣で、エリクの瞳にはじんわりと涙が浮かんだ。
「ううっ……どうしよう。買ってきてもらった材料は全部使っちゃったし、こんな料理、ティアナに見せられないよ……っ」
「やはり、オレたち4人で料理をするのは、無理があったか……」
アルフレートの重いため息に、マティアスは不機嫌そうに目を細める。
「俺は最初から反対だった。美味い物を食わせたいなら、腕のいい料理人を連れてくるなり、そういう店に行った方が早い」
「まったくだな。誰だよ、こんな面倒なことを提案しやがったのは……」
「だ、だって、いつもティアナが僕たちのために一生懸命ご飯を作ってくれるのが嬉しくて……! だから、ティアナに喜んでもらおうと思って、それで……っ」
「お、おいおい、泣くなよエリク!」
ぽろぽろと頬を伝う涙を見て、慌ててルシアがその肩を揺らす。
「……悪かった、エリク。ティアナに何かしてやりたいと思う気持ちは、皆同じだ」
優しく頭を撫でるマティアスに、ようやくエリクは顔を上げる。
「ううん……僕もごめんね、マティアス」
「さて、問題はこれからどうするか、だが……」
4人はお互いの顔を見合わせるが、これといって名案も浮かばず、ため息ばかりが漏れる。
そんな重い空気を打ち破るように、唐突に台所の扉が開かれた。
「ここにいたのか、マティアス。質問状を回収に来たんだが……」
「クラウス……!!」
「……!?」
4人の声が重なり、クラウスは扉に手を掛けたままその場に固まる。
「確かお前、パン屋の息子だったよな」
「唐突になんだ。それがどうかしたのか」
「え? もしかしてクラウスって、料理ができるの!?」
期待に満ちた眼差しが集まり、クラウスは困惑の表情を浮かべる。
「料理は不得意ではありませんが、それが何か……」
「わぁ、じゃあちょうど良かった! 僕たち、とっても困ってたんだ」
「困っていた……?」
「クラウス、次期ファザーンの王としての命令だ。この鍋の中身を、なんとか食える物にしろ」
「なんだと? 俺はお前に命令される覚えなど──」
不機嫌そうに睨み付けるクラウスに、マティアスは質問状の束をちらつかせる。
「この料理が完成したら、質問状を返してやる」
「なっ……!?」
「頼む、クラウス。もう時間がないんだ」
「僕たち、ティアナのために美味しい料理を作ろうとしたんだけど、中々上手く行かなくて……!」
アルフレートとエリクにがっしりと手を握られ、クラウスはようやく諦めに似たため息をつく。
「ティアナのため……ですか。そういう理由なら、仕方がありませんね」
「わぁ、ありがとう、クラウス!」
「ただし、殿下たちにも手伝っていただきます。よろしいですか?」
「ああ、もちろんだ」
クラウスの指示通り、せわしなく手を動かすエリクたちを眺めながら、ふとマティアスは目を細める。
「おいマティアス! さぼってねーで、ちゃんとやれよ!」
「ああ、わかっている」
呪われた前王、バルタザールの血を分けた弟たち──。
幼い頃は、こんなふうに共に過ごせる日が来るとは想像もしていなかった。
(こうしていられるのが、ほんの僅かの間だったとしても……)
マティアスは、深く何かを噛み締めるようにゆっくりと目を閉じ、柔らかく微笑んだ。
END